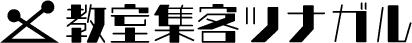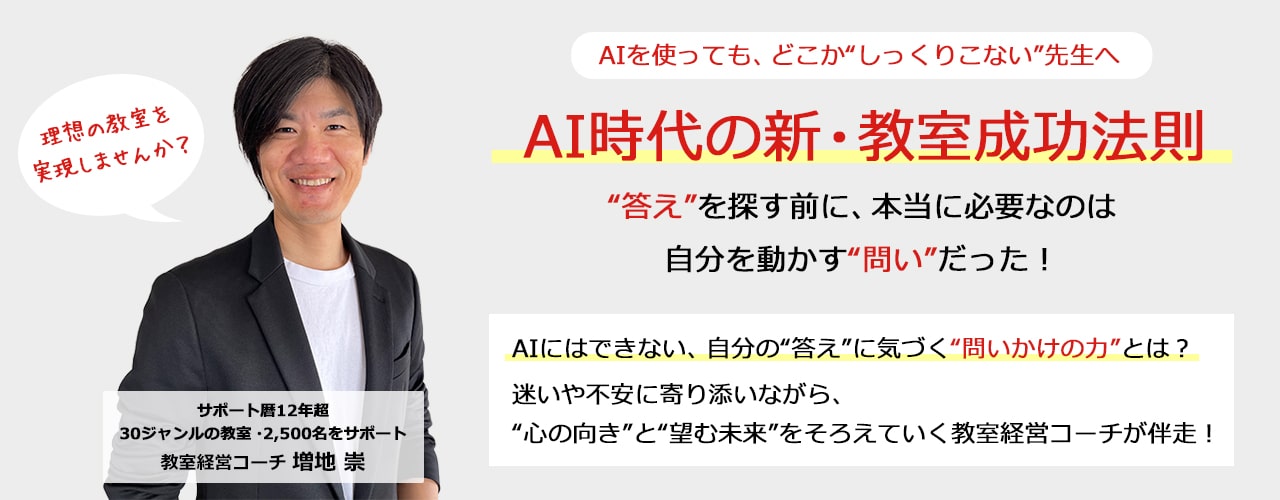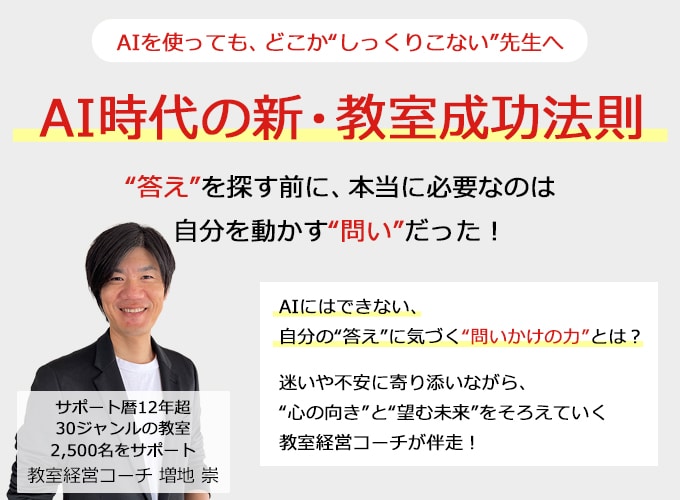教室やスクールを経営している先生方の中で「ウリをうまく表現できていない」、「ターゲット層がわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
集客がうまくいかない原因のひとつは、自身のウリや強みが明確に伝わっていないことにあります。
今回の記事では、教室のウリを正しく打ち出し、集客に繋げるための視点をお伝えします。今の集客に悩んでいる先生には、きっと参考になる内容です。
今回のお話は、つぎのような先生に参考にしていただけると思います。
- ホームページからの反響がイマイチ…
- 自分のウリがよくわからない…
- ウリをどう表現したらいいかわからない…
- ウリを表現しているけれど、反響があまり…
- ターゲット顧客がよくわからない… etc
では、早速はじめたいと思います!
「ウリ」を打ち出す重要性

「先生の教室にしかないウリを打ち出しましょう!」
この言葉を耳にしたことがある先生も多いかと思います。
今や、ネットで調べれば集客に関する情報は、カンタンに見つけることができます。
そして、集客において大切な要素のひとつとして「先生の教室にしかないウリを打ち出しましょう!」ということは、いろんな方がおっしゃっています。
僕もその一人です。
ちなみに僕は「ウリ」のことを「強み」とか「魅力」とか「独自性」などとも表現しています。
いずれの表現も、ほぼ同義だとご理解いただければと思います。
「またこの話?、ウリが大事なんて知ってるよ!でも、それがうまく打ち出せないから困ってるんだよ!」
もしかしたら、そう思われたかもしれません。
でもどうか、もう少しつづきをご覧になってみてください。
今回のお話は「ウリ」のこと“だけ”お話しているわけではありません。
もしお時間のない先生がいらっしゃったら、今回のブログの最後のほうにある「まとめ」をご覧いただくだけでも構いません。
ウリを深堀りする

イメージ図
さて、ご自身のウリを認識しておられる先生は年々、増えているように感じます。
それだけ、集客に関する知識を学ばれている先生が増えていらっしゃるのだと思うんですね。
例えば、つぎのようなウリをお持ちの先生がおられます。
「ウチのウリは個別指導です」
「基礎から丁寧に教えていることです」
「効果がなければ返金保証」
ただ今回はですね、この「ウリ」について少し違った角度であったりもう少し深堀りをしてお話してみたいと思います。
ノドの痛みに湿布!?

例えば、ノドが痛くなったら先生はどうされますか?
トローチを、服用する方がおられるかもしれないですね。
また、転んじゃってヒザをすりむいたらどうされますか?
消毒して、絆創膏を貼るかもしれないですね。
さらには、ねんざしちゃったらどうされますか?
湿布を貼るかもしれないですね。
なぜ、このような行動を取ると思いますか?
それは、上記に挙げた行動が「解決策」だからです。
「ノドの痛み」を鎮める解決策として、トローチを服用する。
「すり傷」による出血や痛みを治すための解決策として、消毒して絆創膏を貼る。
「ねんざ」による痛みや炎症を鎮める解決策として、湿布を貼る。
ここまでよろしいですか?
「解決策」が必要になるのは?

ではつぎに、上記のように「解決策」が必要になるのはどういうときだと思いますか?
それは「問題」に直面したときです。
「ノドの痛み」という問題に直面したから解決策として、トローチを服用しようと考えたわけですね。
「すり傷」による出血や痛みという問題に直面したから解決策として、消毒や絆創膏を用いようとしたわけですね。
「ねんざ」による痛みや炎症という問題に直面したから解決策として、湿布を貼ることにしたんですね。
このことから「問題」と「解決策」は必ずセットで存在していると言えます。
さて、ここまで大丈夫でしょうか?
では、もう少し進めます。
「問題」と「解決策」はセット

「問題」と「解決策」は、どちらかだけが存在することはありません。
人間は、本能的に問題に直面した瞬間から解決策を求めはじめます。
逆の見方をすれば「問題」が起こっていないのに「解決策」は必要ありません。
「ノドが痛いわけでもない、声がかすれているわけでもない」そんな健康な状態ならトローチはあまり必要ありません。
すりむいていなければ、消毒も絆創膏も必要ありませんよね。
また、ねんざしていなければ湿布を貼ることもありません。
つまり、人間は問題に直面しないかぎり解決策を求めないと言えます。
なんだか、ややこしいですね(苦笑)。
でも、あともう少しだけお付き合いください。
ノドの痛みには、トローチが有効!

さらには「問題」を解消するから「解決策」だと言えます。
つまり「解決策」とは「問題」を解消する“有効な手立て”なんですよね。
それを踏まえると、問題を解決するならつぎの2つを把握する必要があると僕は考えます。
- どんな問題が起こっているのか?
- どんな解決策が有効か?
「ノドの痛み」という問題を認識しているから、有効な解決策として「トローチ」を服用するんですよね。
ですが「ノドが痛い」のに「絆創膏」を貼っても、おそらくノドの痛みは治らないと思うんです。
また「ねんざ」しているのに「かぜ薬」を服用しても、やはりねんざは治りにくいと思います。
これは、有効な解決策を用いていないからですよね。
何の病気やケガかわからないときはどうする?

さらに「問題」が何なのか?、明確にわからない場合もありますよね。
そういうときには、お医者さんに行ったりします。
そして、問診・検査などによってカゼなのか、インフルなのか、はたまた肺炎なのかといったことが明らかになります。
そうすると、お医者さんは症状にもとづいて適切な処置をしてくれます。
適切なお薬を処方してくれたり、注射や点滴をしてくれたり…。
きっと、ねんざなのにかぜ薬を処方するお医者さんはいないと思います。
それは「問題」と、それに対する有効な「解決策」を理解しているからです。
さて、実はここまでが前置きになります(苦笑)。
以上のお話は、教室集客に大きく関係します。
「誰の」どんな「問題」を解決している?

今回のブログの冒頭のほうで「先生方は、ご自身のウリをよくご存知だ」とお伝えしました。
「ウチのウリは個別指導です」
「基礎から丁寧に教えていることです」
「効果がなければ返金保証」
そして(くり返しますが)これらは「解決策」です。
しかも「誰か」が直面している何らかの「問題」を効果的に解消する手立てなんですね。
「誰か」とは、この場合お客さまですね。
ちなみに「生徒」と書かず「お客さま」と書いたのには理由があります。
お子さん向けの教室の場合「お客さま」とは、生徒であるお子さんではなくその保護者の方だからです。
保護者の方が直面している「問題」を「解決」したくて、お子さんを教室に通わせておられるんです。
いずれにしても「誰か」は「お客さま」です。
では「お客さま」とは、どんな方なのでしょう?
そして、お客さまはどんな「問題」に直面しているのでしょう?
「誰の」どんな「問題」を解決しているか?の実例

もう一度、先ほど挙げたウリのひとつをご紹介いたします。
「ウチのウリは個別指導です」
これが「解決策」であるならば「誰の」どんな「問題」とは、こういうことかもしれません。
誰の?=お客さまとは?
- 中2のお子さんのお母さん
- 大手の一斉授業の塾に子どもを通わせている
- だけど、学期末の成績がまた下がった
問題とは?(お母さんの心の声)
- 大手の一斉授業の塾に通わせてきたけれど、学期末の成績がまた下がった…。
- 子どもは「勉強のやり方がわからない」と言っている。
- しかも、テストの解答を見たらこの子、中1で習ったことができてないじゃない!
- だったら、子どもの学力に合わせて教えてくれる塾に代わったほうがいいのかも…。
- ノートの取り方とか勉強のやり方を教えてくれトコないかしら…。
上記のような方のお悩み(問題)に対して「個別指導」を伝えたら、問い合わせや申し込みが得られる気がしませんか?
けれど、このとき
- 大手塾によろこんで通っている
- 成績は良好
または
- 塾に通う必要性がない(=問題に直面していない)
このような方に「個別指導」を伝えても、問い合わせや申し込みはあまり期待できなさそうですよね。
ターゲットにピッタリの解決策を提案しよう!

ということで、ここからが今回の一番のポイントです。
何度もくり返しますが、ご自身のウリをご存知の先生はたくさんいらっしゃいます。
そこで、もう一段掘り下げて考えてみてください。
そのウリは「誰の」どんな「問題」の「解決策」ですか?
この3つがピタリと一致することで、ホームページからの反響が大きく高まります。
逆に、ホームページからの反響がイマイチの場合、この3つが一致していないことが原因であることがほとんどです。
どうか、ねんざなのにかぜ薬を買おうとしないでください(笑)。
ねんざには、湿布。
かぜには、かぜ薬。
すり傷には、絆創膏。
お客さまの問題を明らかにし、有効な解決策を提示してあげてください。
大切なことなのでもう一度だけ、お伝えします。
そのウリは「誰の」どんな「問題」の「解決策」ですか?
この3つを、ぜひ考えてみてください。
まとめ

今回の内容を振り返ると、教室のウリを効果的に表現するためには、まず「誰の」、「どんな問題」の「解決策」かを明確にすることが重要だとわかります。
生徒や保護者が直面している具体的な問題を理解し、その解決策として提供できるウリを伝えることが、集客のカギとなります。
ホームページや広告で反響を得るためには、この3つが一致していることが不可欠です。
自分のウリを深く掘り下げ、ターゲットにぴったりの解決策を提案することで、より多くの反響を得ることができるでしょう。