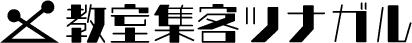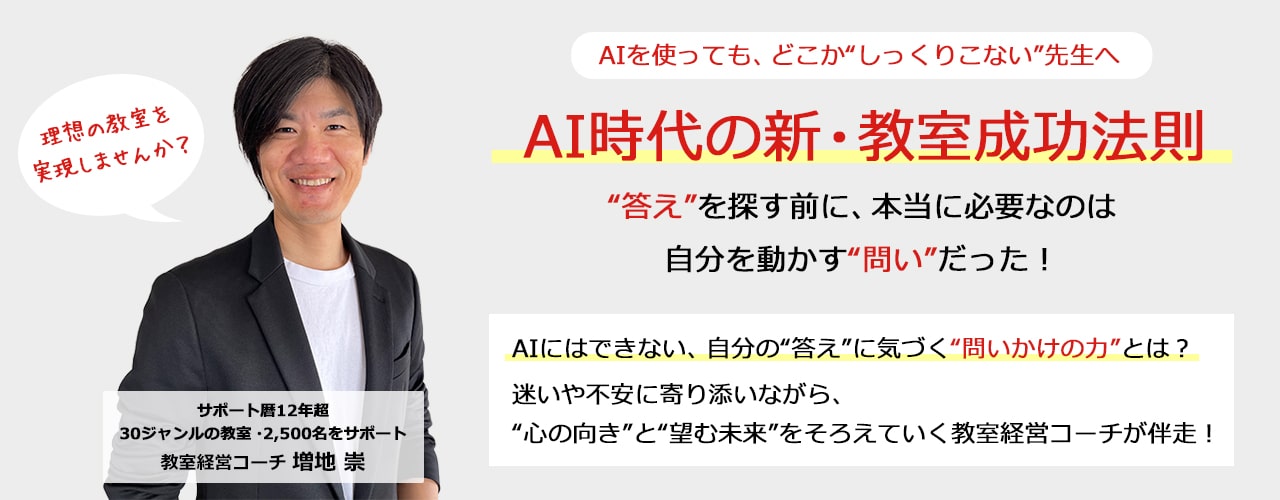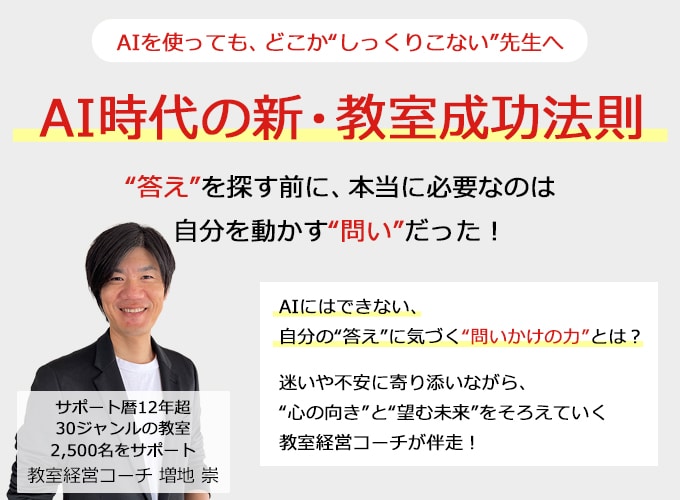先生は、例えばSNSなどで他の教室の情報を目にして、焦りや不安を感じたことはありませんか?
また、「他人と自分を比較してしまって、ついつい自分にダメ出しをしてしまう」といった経験を、多くの教室の先生方が実際にされているということを、僕自身、よく耳にすることがあります。
そこで今日は、「比較をやめて、自分らしい教室づくりに集中する心の整え方」というテーマで、お話をさせていただきたいと思っています。
- 「比べること」は本当に悪いこと?
- 比較から生まれる「自分の良さ」
- 自問を続けることの大切さ
- 比較する力が開いた未来——黒柳徹子さんの話
- 自分にしかできないことに気づく力
- 他者がいるからこそ自分の個性が際立つ
- 他者基準ではうまくいかない理由
- 同じ環境でも違う結果が出た理由
- 他者基準が無意識に引き起こす行動
- コロナ禍でも教室を開け続けた学習塾の先生
- 通塾の判断は保護者に委ねた
- 自分基準で生きることの力
- 他人と比べる理由とは?
- SNSが与える無意識の影響
- 自分基準にシフトするための3つのコツ
- 「自分基準」が育つと得られる大きな変化
- 「他者基準」で生きることの落とし穴
- 比較せず、自分の軸で生きられるようになる
- 目指すべきは「自分のスタンスを持つ」こと
「比べること」は本当に悪いこと?

さっそくですが、まず「周りと自分を比べること」そのものは、僕は決して悪いことではないと思っています。
ただし、比べることによって、周りの人の方が素晴らしく見えてしまったり、それに比べて自分はダメだと感じてしまう、あるいは「比較はよくないことだ」と決めつけてしまう——そのような思考が、マイナスになってしまうことがあるとも考えています。
僕は、「周りと自分を比べることができる」というのは、実はある種の才能の一つだと考えています。
なぜなら、自分と周りを客観的に見ることができるというのは、自分自身に対する観察力や、他人に対する分析力を持っているということだからです。
そして、自分と他の人との違いを理解することができる、ということでもあるのです。
この「他との違いを知る」力、「周りと比べて自分はどうなのかを見極める」力というのは、実は教室運営において非常に重要な力だと僕は思っています。
例えば、他の教室と自分の教室の違い、あるいは他の先生と自分の違いを知ることができれば、それは結果として、先生ご自身にしかない「独自性」や「強み」を発見することにつながります。
そして、それによって「どんな生徒さんに、どんな価値や満足を提供できるのか」ということが明確になってくるのです。
比較から生まれる「自分の良さ」

周りと比べるからこそ、「自分の良さって何だろう?」と考えることができる。
その良さに気づいたときに、「先生のレッスンを受けてみたい」と感じてくれる生徒さんたちが集まってくる。
それが、先生にとっても生徒さんたちにとっても、幸せな教室づくりの第一歩になるのではないでしょうか。
そこで、そのような「比べる力」を前向きに生かすために、ここでひとつ、とても効果的な問いかけをご紹介したいと思います。
それが、次の質問です。
「私がすでに持っている“人と自分を比べる力”を、どのように生かせば、自分も生徒ももっとハッピーになれる教室を作れるだろうか?」
少し長いですが、大切なのでもう一度お伝えしますね。
「私がすでに持っている“人と自分を比べる力”を、どのように生かせば、自分も生徒ももっとハッピーになれる教室を作れるだろうか?」
この問いかけを、ぜひ日々の中でご自身に投げかけ続けていただきたいと思います。
そうすることで、先生ご自身にも、生徒さんたちにとっても、より幸せな教室のアイデアが思いつくようになってくるのです。
自問を続けることの大切さ

この問いをした時、すぐにアイデアが浮かぶ場合もあれば、すぐには出てこない場合もあるでしょう。
ですが、すぐに答えが出なかったとしても、自分に問いかけ続けることで、ある日ふと、「これかもしれない」とひらめくことがあるのです。
また、一度思いついたアイデアを実行してみたけれど、うまくいかなかった——そんなことも、きっとあるでしょう。
でも、実は「うまくいかない経験」を通じてこそ、本当に望んでいた結果にたどり着く“真のアイデア”に出会えるということもあるのです。
だからこそ、先ほどの問いかけを、ぜひ日々の中で自分自身に問い続けてみてください。
ちなみに、この質問は少し長いので、紙に書き出して目につく場所に貼っておく、あるいはスマートフォンなどにメモしておいていつでも見返せるようにするといった工夫をすることで、この問いが心の深い部分にまで届きやすくなり、それによってインスピレーションやアイデアが自然と湧きやすくなります。
比較する力が開いた未来——黒柳徹子さんの話

イメージ
僕は、「人と自分を比べる」というのは、非常に大切な能力だと思っています。
そして、その能力を生かした印象的なエピソードとして、僕が思い出すのが、黒柳徹子さんのお話です。
厳密に言うと、黒柳さんが小学生の頃に通っていた「トモエ学園」での話で黒柳さんの同級生だっが、山内泰二(やまうち・たいじ)さんのお話です。
山内さんは、現在も世界的に有名な物理学者として、第一線で活躍していらっしゃいます。
実は山内さん、トモエ学園に来る以前、別の学校では「発育不良」と見なされて入学を断られたという経歴をお持ちなんです。
つまり、周りと比べたときに、発達や学力の面で「劣っている」と判断されていたわけです。
ですが、トモエ学園の校長であった小林宗作(こばやしそうさく)先生は、そうした山内さんに対して、「君にしかできないことを見つけることが大事なんだよ」と声をかけたのだそうです。
その言葉を受けて、山内さんは「自分にしかできないことって何だろう?」と考え、「自分は勉強が得意かもしれない」と気づいたといいます。
さらに、山内さんのお父さんは電気工学技士で、自宅にはたくさんの実験器具があったそうです。
その影響もあって、学校の理科室にある実験器具が、お父さんの仕事道具と似ていることに興味を持ち、実験に没頭するようになったのだそうです。
その日々の体験が、後に物理学者としての原点となった——そんなことを、僕は以前あるテレビ番組で拝見しました。
自分にしかできないことに気づく力

イメージ
もともとは「発育不良」と判断され、他の学校で断られた山内さん。
ですが、他人との比較に対して否定的にならず、「自分にしかできないこと」に意識を向けることで、その後の人生が大きく開かれていったのです。
このように、人と比べることによって「自分にしかないもの」「自分にしかできないこと」に気づくきっかけが生まれる。
そしてそれが、能力の開花につながっていくのだと、僕は信じています。
だからこそ、僕たちもまた、「比較する力」を正しく使いながら、自分らしい教室づくりを進めていけたら素晴らしいと思うのです。
ここで大事になってくるのが、「自分にしかできないこと」や「自分の好きなものを見つける」ためには、実は“人と比べる”ということが必要になってくる、という点です。
なぜかというと、世の中というのは、他者や他の物事との「比較」を通じて、自分の得意なことや好きなことを認識できるようにできているからです。
例えば、「右」という概念は、「左」という概念があるからこそ成立しますよね。
また、「勝者」という存在も、「敗者」という存在がいるからこそ成り立つのです。
オリンピックで全員が金メダルということはありえません。
必ず順位がつき、金、銀、銅とメダルが分かれ、そして中にはメダルを取れなかった選手もいます。
つまり、ある存在があることによって、もう一方の存在が認識され、意味づけされるという仕組みになっているのがこの世の中だと言えるのです。
他者がいるからこそ自分の個性が際立つ

そう考えると、他者が存在するからこそ自分の存在も成り立ちますし、他者がいるからこそ自分との違いを認識することができると言えます。
だからこそ、「人と比べる」ことによって、自分の得意なことや好きなこと、他の人との違いを見つけやすくなるのだと思います。
そう考えると、やはり先ほどの「問いかけ」が大切になってくるわけです。
「私がすでに持っている“人と自分を比べる力”を、どのように生かせば、自分も生徒ももっとハッピーになれる教室を作れるだろうか?」です。
人と比べる能力というのは、誰しもが常に持っています。
そしてそれをどのように活用するかによって、自分の強みや好きなこと、得意なことを見つけることができるのです。
このような問いを通じて、人と自分を比べることをきっかけに、先生ご自身の良さや魅力、強みに気づいていただけるのではないかと思います。
そして大事なのは、このように他者との比較を活用しながら、最終的に“自分らしい教室”を実現するということです。
つまり、「これがやりたい!」と心から思えるような、自分基準の教室をつくるということです。
人と比べた結果、最終的に“自分がやりたい教室”を実現することが、何よりも大切なのではないでしょうか。
他者基準ではうまくいかない理由

逆に、人と比べて「あの人はこんなに素晴らしいのに、自分はダメだ」といった活用の仕方をしてしまうと、苦しくなります。
そして「今の自分はダメだから、周りに喜んでもらうにはこうしなければならない」「評価されるにはこうしなければならない」と、周りが求めるものに自分を合わせようとして生きることがあります。
これを「他者基準」と言います。
ズバリ申し上げますと、教室経営にこの“他者基準”を持ち込むと、経営がうまくいかなくなり始めるんです。
これが如実に現れたのが、コロナ禍の時でした。
コロナ禍では、誰もが経験したことのないような事態が起きました。
緊急事態宣言が発令され、学校が休校になったり、店舗が臨時休業になったり、ステイホームが推奨されたりと、人々の行動が大きく制限されたわけです。
その当時、ニュースでは「このまま経済が停滞する」「不況が来るだろう」といった報道が多く流れていました。
実際、多くの先生方が教室を休みにせざるを得なくなったと思いますし、それによって売上が下がったという方もおられたでしょう。
もちろん、誰しもが未経験の状況だったわけですから、仕方がない面もあります。
「コロナだから仕方ない」と思うのも当然のことかもしれません。
同じ環境でも違う結果が出た理由

しかし、その一方で、コロナ禍においても売上を落とさなかった人や、むしろ過去最高の売上を上げた企業や教室があったのも事実です。
もしニュースの通りに「経済が落ち込む」のなら、すべての人の売上が下がっていなければおかしいはずです。
けれども、実際には売上を下げなかった人、むしろ伸ばした人がいたのです。
僕のクライアントの先生方の中にも、コロナ禍で過去最高の売上を記録した教室がありました。
では、この違いはどこから来たのか?
僕なりに分析した結果、その違いは、「生きることの判断基準」「喜びの基準」が“自分基準”だったか“他者基準”だったか、そこにあったのではないかと考えています。
例えば、「自分にとって大切なことは何か」「自分が生きていく上でこれが喜びだ」といった基準を、自分の中に持っている人は、周りがどうあれ、自分の判断で進んでいくことができます。
一方、“他者基準”の人というのは、生きる上での判断や喜びの基準が他人にあります。
「周りがそうしているから自分もそうする」「周りが喜ぶから自分もそうする」といった行動の選び方をします。
別の言い方をすれば、他者基準の人は「私は周りに合わせて生きていきます」「自分の気持ちは出しません」と宣言しているのとほぼ同じです。
だとすれば、コロナ禍のときに「不況になる」「売上が下がる」という周りの声に、自ら合わせにいこうとするのも自然な流れになります。
つまり、「私は周りに合わせて生きます」という姿勢が、無意識に「売上を下げに行く」という行動に繋がってしまうのです。
他者基準が無意識に引き起こす行動

この考え方は、僕自身とても重要だと思っていますので、あえてもう一度強調してお伝えしたいのです。
「不況だから」「コロナだから」売上が下がったのではありません。
「不況になる」という周りの声に合わせようとした結果、自分で売上を下げにいってしまったのです。
生き方の判断基準が“他者基準”になってしまうと、無意識にそうしたことを引き起こしてしまうのです。
誰だって売上を落としたくはないはずですが、無意識に周囲に合わせてしまう、「他者基準的」な生き方をしていると、自ら進んで売上を落としにいくような行動をとってしまうことがあります。
では、「自分基準」の人はどうかというと、たとえコロナ禍のような状況でも、売上を伸ばしていくんです。
今回は、実際の事例をご紹介したいと思います。
コロナ禍でも教室を開け続けた学習塾の先生

イメージ
クライアントの先生で、学習塾を経営されている方がいらっしゃいます。
2020年の4月初旬、ちょうど入学シーズンに、緊急事態宣言が発令されたとき、世間が混乱する中で、その先生はご自身の教室を朝から晩まで開け続けていました。
なぜかというと、「学校が休みの今こそ、成績を伸ばす大チャンスだ」と考えたからです。
通常の夏休みや冬休み、春休みといった学校が休みの期間は、過去の学習内容を復習して、つまずきを克服する絶好のタイミングです。
そのチャンスが、今回たまたまコロナによって生まれた。
「だからこそ、今は勉強を止めてはいけない」と、その先生は強くお考えになったそうです。
とはいえ、世の中では感染拡大を防ぐために、緊急事態宣言が出されていたわけですから、その先生も当然、それを守っていらっしゃいました。
当時、感染拡大防止策として言われていた「三密の回避」を徹底し、教室の窓という窓、ドアというドアをすべて開け放ち、換気扇も常に回して授業をされていたのです。
さらに、生徒が一度に教室に集中しないように工夫もされていました。
朝から晩まで教室を開放し、生徒が「いつ来てもいいし、いつ帰ってもいい」という柔軟な運営を行ったのです。
その結果、一つの時間帯に生徒が密集することもなく、感染拡大のリスクを抑えながら授業を継続できていました。
このように、感染予防に最大限配慮しつつも、「子どもたちの学びを止めない方法」を模索し、朝から晩まで教室を開放して授業を続けていたのです。
通塾の判断は保護者に委ねた

もちろん、この時期は通塾も自由選択とされていました。
先生は教室を開けていましたが、生徒が通うかどうかは生徒および保護者の判断に委ねていたのです。
そのような取り組みをしていましたら、新規の問い合わせが入ったそうです。
実はその問い合わせをしてきたのは、先生の塾のすぐ近くにある大手塾に通う予定だったご家庭でした。
その保護者の方は、もともと大手塾に入塾手続きも済ませ、これから通い始めるというタイミングで、緊急事態宣言が出されたそうです。
大手塾は、全国に多くの教室を持っているため、一斉休校という対応をとりました。
その結果、塾からの連絡も一切途絶えてしまい、保護者の方は不安に感じていたそうなんですね。
そんなとき、近所に窓やドアを全開にして授業をしている塾があることに気づき、相談のつもりで問い合わせをされたのです。
先生は、「今の時期ではありますが、朝から晩まで教室を開けて授業をしています」と説明されました。
するとその保護者の方は、大手塾の入塾をキャンセルし、先生の塾に転塾されたのです。
自分基準で生きることの力

これこそが「自分基準」のスタイルだと思うんです。
世の中は「三密を避けてください」「ステイホームしてください」と言っていた中で、その状況を受け止めつつも、「できることはないか」と考え、自分なりに最善の方法を模索し、行動に移された。
「自分基準」の人は、このように「自分が本当にやりたいこと」があると、それをどうしたら実現できるかを考え、実際に行動に移し、実現してしまうのです。
これが、自分基準の人の大きな特徴です。
そして実は、こういった「自分基準」の人のもとには、なぜか人が自然と集まってくるんです。
先ほどの例のように、大手塾から転塾してきたケースもまさにそうですね。
自分基準で生きる人は、それだけ魅力的に映るんだと思うんです。
他人と比べる理由とは?

「人と比べる」という行為は、何のために行うのかを突き詰めていくと、「自分基準の教室経営」を実現するためなんです。
他人と比べることを通じて、自分はどんなことが得意か、何が好きか、そして「周りがこういう教室をしているけど、自分はこんな教室をやりたい」といった、自分のやりたい方向性を見つけ出していくのです。
それこそが、自分基準の教室経営であり、最終的にはそれを実現していくことになります。
ただし、「この人は100%自分基準」「この人は100%他者基準」といった、明確な線引きはなかなかできません。
むしろ、仕事においては自分基準である一方、家族関係では子どもの意見やパートナーの意見を優先している、というように分野ごとに基準が異なることのほうが多いと思います。
ですから、大事なのは、今より少しでも自分基準的な生き方を選択できるようになることです。
それによって、先生が望んでいるような結果や、理想の教室経営が実現できると僕は思います。
特にこれまで「他者基準」的に生きてこられた方にとっては、「自分基準でいきましょう」と言われても、すぐには受け入れられないかもしれません。
また、自分基準の大切さを理解できたとしても、それをすぐに実行に移すのは難しいと感じるかもしれません。
日本の教育や社会環境は、どうしても他者基準的な思考が育ちやすい構造だったと思うんです。
それは「和を大切に」「協調性を重んじる」という文化の中で、周囲に合わせて自分を抑えることが良しとされてきた背景があると思います。
SNSが与える無意識の影響

さらに、近年ではSNSなどの影響も大きいですよね。
自分が望まなくても、「いいね」や「再生回数」などの数字が目に見える形で提示されるので、どうしてもそれに引っ張られてしまいがちです。
「たくさんのいいねが欲しい」「多くの人に見てもらいたい」と、無意識のうちに他者の評価を基準にしてしまう。
これはとても危険なことであり、十分に注意が必要です。
つまり、現代は日常生活を普通に送っていても、知らないうちに他者の基準に引っ張られてしまうことが、本当にたくさんある状態だと思うんですよね。
そして、そういった他者の基準に引っ張られるような環境にさらされ続けると、気づけば周囲の目や評価ばかりが気になってしまって、自分が本当にやりたいことよりも、「周りにどう評価されるか」を優先してしまうようになることがあるんです。
結果的に、「自分はどうしたいのか」「何をしたいのか」といったことすら分からなくなってしまうということが、実際に起きたりするんですよね。
これまで、そういった他者基準的な生き方をされてきた方も多いかもしれませんし、実は僕自身もまさにそういったタイプだと感じています。
現在も、僕の中には他者基準的な部分もありますが、だからこそ強く思うのは、やはり他者基準で生き続けていると、自分が本当にどうしたいのかが分からなくなってしまうということなんです。
自分基準にシフトするための3つのコツ

ですから、ここまでのお話を踏まえて、以下で「教室経営において、他者基準から自分基準にシフトしていくためのコツ」を3つご紹介したいと思います。
コツ① 日常の些細な選択を「自分基準」で行う

まず1つ目は、「日常の些細なことで、自分がやりたいこと・欲しいものを意識的に優先する」ということを、ぜひやってみていただきたいんですね。
例えば、朝起きたときにその日の気分で「食べたいものを決める」といったことです。
もし毎朝決まったものを食べているという方がいらっしゃれば、ぜひその日その時の気分で「今日はご飯を食べたい」と思ったらご飯にする、「今日はパンの気分だな」と思ったらパンにする、あるいは「ホットケーキが食べたい」と思えばホットケーキを食べる、というようにしてみてください。
そうやって、自分がその瞬間に望んでいるものを優先して選択していくことで、「自分は本当はどうしたいのか」という本音に気づきやすくなってきます。
朝ご飯に限らず、「今日は朝からシャワーを浴びたい」と思ったらシャワーを浴びる、「ちょっと公園を散歩したいな」と思ったら散歩に出てみる、というように行動してみてください。
こうした行動を積み重ねることで、「今、自分は何を求めているのか」をしっかりと把握することができるようになります。
それが、自分基準を持つための第一歩だと思います。
そう考えたときに、例えば先生は普段、朝何時に起きていらっしゃいますか?
そして、なぜその時間に起きていると思われますか?
仮に「7時に起きている」としましょう。
その理由が「朝ごはんを作らないといけないから」とか、「家族にお弁当や朝食を用意しないといけないから」とか、「仕事が何時から始まるから」ということであれば、それは他者基準で動いているということになります。
つまり、他人の都合に合わせて自分の行動を決めている状態ですね。
もちろん「家族に美味しい朝ごはんを食べてもらいたいから、7時に起きる」という理由であれば、それは自分の意志に基づいた自分基準の行動です。
このように、朝起きる時間ひとつをとっても、自分基準で「起きたい時間に起きる」ということを、試しにやってみると良いんじゃないかと思います。
それくらい、日常生活では無意識のうちに他人の都合に自分を合わせてしまっていることが少なくないと、僕は感じています。
だからこそ、意識的に自分基準で選択していくことが大事であり、そうしていくことで、自分が本当に求めているものを把握しやすくなるんです。
これが、1つ目のコツになります。
コツ②:アイデアを授業にさりげなく取り入れていく

イメージ図
1つ目の方法で「自分がどうしたいのか」が正確に把握できるようになってきたら、日々の教室経営や授業の中で「こういうことをやってみたいな」「こういうことを取り入れてみたいな」というアイデアが浮かんでくるかもしれません。
そこで2つ目のコツは、そのアイデアを日常の授業の中に、少しずつ、さりげなく紛れ込ませていきます。
自分基準が大事だからといって、ある日突然すべてを自分のやりたいことにバッと切り替えてしまうと、それはそれで生徒の皆さんがびっくりしてしまう可能性があります。
もともと人間は「習慣の生き物」であり、急激な変化には弱いという性質があると思うんですね。
例えば、季節の変わり目に体調を崩しやすいのも、そういった理由からだと思います。
ですから、自分がやりたいレッスンがあることはとても良いことですが、それをいきなり全部変えてしまうと、生徒にとっては負担が大きくなってしまい、反発が起きたり、クレームが出たり、場合によっては辞めてしまう方も出てきかねません。
段階的なレッスンの変化で目指す理想へ

そういったことを防ぐためにも、生徒さんにとって負担の少ない形で、なおかつ先生ご自身も「やりたいレッスンの方向」に進めるようにするには、少しずつ、さりげなく取り入れていくのが効果的です。
まずはレッスンの中に、自分が取り入れたいと思っている要素を、さりげなく紛れ込ませていく。
そして、生徒の皆さんが違和感なく馴染んでいけるようになったら、徐々にその要素を増やしていき、最終的には「先生がやりたかったレッスンの形」に持っていく。
このように、ある程度の期間を設けて、少しずつ変化させていくことが、2つ目のコツです。
もし急激な変化で周囲から反発があったりすると、「やっぱり自分は自分のやりたい教室運営なんてできないんだ」と、自信をなくしてしまうことも起こりかねません。
だからこそ、徐々に自分基準を取り入れていくという「作戦」を実行していただけるといいのではないかと思います。
これが2つ目のコツです。
コツ③:リスクを想定し、事前に備える

Close up of professional afro woman sharing business ideas with international colleagues in office
そして3つ目のコツですが、それは「自分基準の教室運営」や「自分基準の授業・レッスン」を取り入れて変化させていったときに、どんなリスクが起きうるかをあらかじめ想定し、その対応策を考えておく、ということです。
例えば、先生が「こういうレッスンをやっていきたい」と考えて、その要素を今までのレッスンの中に少しずつ取り入れていこうとしたとします。
このとき、実際にそうしたレッスンを行う前に、「これをやったら生徒さんや保護者の方はどう思うだろうか?」「どんな反応をするだろうか?」「どんなことを言われるかもしれないか?」と、あらかじめ頭の中でシミュレーションしておくんですね。
もしかしたら、生徒の方の中には、「なんでそんなことをするんですか?」「それのどこが良いんですか?」といった否定的な意見や、先生のやりたいことに対して批判的な反応をする方もいるかもしれません。
そういった反応をされたときに、どのように対応するかを事前に考えておくんです。
これは、いわば「避難訓練」のようなものです。
実際に災害が起きたときに冷静に避難できるように、日頃から避難経路や対応策を訓練しておくように、教室運営でも「どんなことを言われるかもしれない」「どんな反応があるかもしれない」というリスクを想定しておき、それに対して「どう説明するか」「どう納得してもらうか」を事前に準備しておく。
それによって、適切な行動を取ることができ、結果として自分基準で教室を運営しやすくなります。
これが、3つ目のコツになります。
参考例:無料の補習を有料にしたいときの伝え方

例えば、学習塾の先生が、これまでテスト前に「テスト前補習」というものを行っていたとしますよね。
そしてそれは、サービスの一環として、無料で実施されていたとしましょう。
しかし、先生ご自身としては、時間や労力がかかるため、今後は無料ではなく有料で実施していきたいと考えたとします。
そうなると、今まで無料でテスト対策の補習を受けられていた方々にとっては、「今まで無料だったものに、なぜこれからお金を払わないといけないのですか?」というような意見が出てくる可能性もありますよね。
そういった反応があることをあらかじめ想定できれば、どう説明するかを事前に決めておく必要があります。
一例として、こういうふうに説明してみてはどうでしょうか。
「これまでは、無料で実施できる範囲内で補習を行っていました。そのため、無料の範囲では提供できなかった教材や資料もありました。
ですが、今後は有料で実施することにより、これまで提供できなかったテスト対策用の教材を活用し、お子様に実際に取り組んでもらうことが可能になります。
それによって、より効果的なテスト対策授業を提供できるようになり、これまで以上の点数アップも期待できます。」
このように説明することで、「有料でも、それ以上の効果が期待できるのであれば価値がある」と、理解・納得してもらえるかもしれません。
納得を得るために準備を怠らないことが鍵

もちろん、ほかにもさまざまな説明の仕方があると思います。
いずれにしても、あらかじめ想定できるリスクをできる限り挙げ、それに対する対応策を準備しておくことが大切です。
そうすることで、先生ご自身も安心して、自分が本当にやりたい授業や教室経営を進めやすくなると思います。
このような取り組みを重ねていくことで、だんだんと「自分のやりたい教室経営」や「自分のやりたい授業」が実現できるようになってきます。
その結果、「自分基準」が先生の中で育っていくのです。
「自分基準」が育つと得られる大きな変化

そして、この「自分基準」が育つと、何が良いかというと、自分基準が育つほどに、無意識のうちに「人生は自分でコントロールできる」という感覚も育っていくのです。
この感覚というのは、教室経営に限らず、先生ご自身が理想の人生を実現していくうえでも非常に重要なものだと、僕自身は考えています。
「人生は自分でコントロールできる」と無意識に思えている人は、たとえコロナ禍で緊急事態宣言が発令され、さまざまなことが制限されたとしても、その状況下であっても自分の人生をうまくコントロールしていくんです。
そういった人たちは、制限がある中でも「自分にできることは何だろう?」「自分がコントロールできることは何か?」ということを考え、工夫し、できる限り望ましい状況を自ら作り出そうとするのです。
先ほど紹介した、学習塾を朝から晩まで開け続けていた先生は、「自分にできることは何か?」と考えながら、理想の状態を自分の手で実現しようと行動されていたわけですよね。
逆に、「他者基準」で生きていると、「人生は自分ではコントロールできない」という感覚が育ってしまいます。
それは言い換えるならば、「人生はもうどうしようもない」「自分の人生は周り次第だ」「私は周りに振り回される」という感覚が、無意識のうちに根づいてしまうということです。
「他者基準」で生きることの落とし穴

ここまでお読みになられて、これをご覧の先生は「自分基準」と「他者基準」、どちらの基準で教室を経営されたいと思われますか?
あるいは、ご自身の人生を「自分基準」で生きたいですか?それとも「他者基準」で生きたいですか?
また、ご家族や教室に通ってくれている生徒さんたちには、どちらの基準で生きていってほしいと思われますか?
きっと、ほとんどの方が「自分基準」の生き方を望まれるのではないかと思います。
ちなみに、「自分基準」というのは、決してわがままな生き方ではありません。
先ほどの、朝から晩まで教室を開け続けていた先生も、ご自身は「開けたい」と思っていたけれど、社会的には「ステイホーム」や「感染拡大防止」が求められていました。
だからこそ、その先生は最大限の感染予防策を講じたうえで、「通塾は自由です」と保護者や生徒に選択肢を提示したうえで、「今は勉強を止める時期ではない」と判断して授業を継続されたわけです。
つまり、自分基準とは、わがままというわけではなく、自分も幸せで、そして周囲の人たちも幸せになるような生き方のことなのです。
比較せず、自分の軸で生きられるようになる

そして、そういうふうに「自分基準」で生きているときには、人と自分を比較することがなくなります。
「周りがどうであれ、自分はこうする」と、他人と比べずに、自分の在り方をしっかり持てるようになるんですね。
これは、非常に興味深い特徴だと思います。
また、自分基準で生きている人は、「自分はこういうことが好き」「こういうのが得意」「こういう教室をやっている」と思うと同時に、他の教室の先生に対しても「(自分とは)別のことが好きで、それが得意で、そういう教室をやっているんだな」と受け止めている傾向があります。
「どちらが優れている」「どちらが劣っている」と比較するのではなく、「どちらも素晴らしいよね」と、自然とそう思えるようになるんです。
今日のテーマは「比較をやめる」ということでしたが、最後にもう一度お伝えしたいのは、比較すること自体が悪いわけではないということです。
むしろ、周囲と比べることをきっかけに、自分基準を育てることに繋がります。
そして、自分基準がしっかり育っていくと、最終的には「人と比べない生き方」へと卒業していけるのです。
目指すべきは「自分のスタンスを持つ」こと

つまり、最終的に目指すべきは、「他人がどうであっても、自分はこうしたい」という、自分自身のスタンスを確立していくことなのです。
今日一番お伝えしたかったのは、この点です。
その過程で、比較という行為が役立つことがあるということも、改めてお伝えしておきたいと思います。
併せてくり返しますが、周りと比べて「自分はダメだ」と思ったり、周りの期待に応えようと自分の気持ちを偽って生きようとするべきではありません。
ですので、ぜひこの「自分基準」という考え方を、教室経営にも取り入れていただきたいと思います。
そうすることで、先生ご自身も、そして生徒やそのご家族といった周りの方々も、ハッピーになれる教室を実現できるのではないかと思います。
僕としては、そうした「自分基準」の教室がこの世の中にたくさん増えていき、各教室が「自分らしさ」を体現する場になっていくことを願っています。
ということで今回は、「比較をやめて、自分らしい教室づくりに集中する心の整え方」というテーマでお伝えしました。