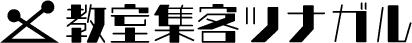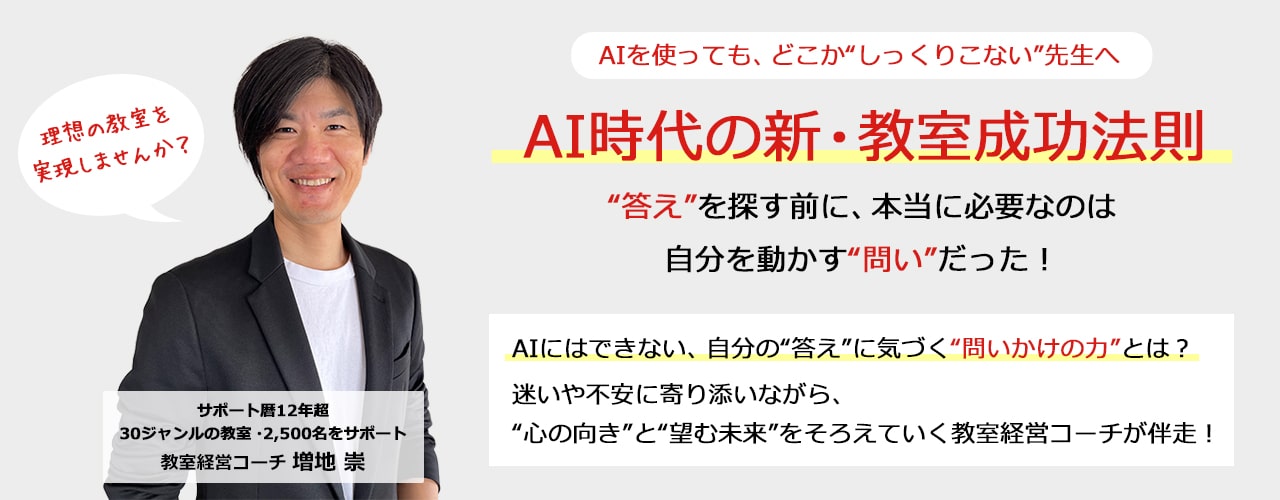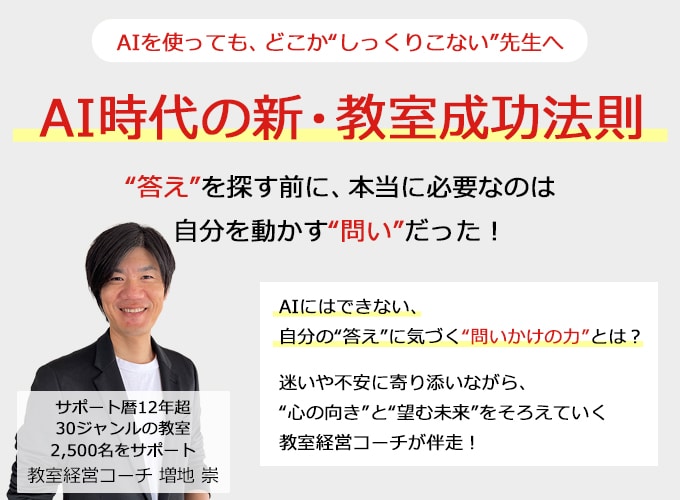目標を掲げ、それに向かって努力するのは素晴らしいことです。
しかし、思うように達成できないと焦りや落胆を感じることもあるでしょう。
特に、周囲の人が順調に成果を上げているように見えると、自分と比べてしまい、余計に辛くなることもあります。
そんなとき、大切なのは「なぜ達成できないのか?」ではなく、「何のために達成させないのか?」という視点を持つことです。
今回は、ある学習塾の先生の実例をもとに、この考え方がどのように役立つのかをお伝えします。
自分に問いかけてみる言葉
目標を掲げ、それに向かって頑張るものの、達成できないと辛いですよね。
そんな時、周りの人が目標を達成している姿を見たり、生き生きと目標に向かって進んでいる姿を目の当たりにすると、つい自分と比較してしまい、余計に辛く感じることもあると思います。
こういう時に、ぜひ自分自身に問いかけてみてほしい言葉があります。
それは、「何のために、自分は目標を達成させないのか?」という問いかけです。
もう一度言いますね。
「何のために、自分は目標を達成させないのか?」
これは、「なぜ目標を達成できないのか?」という問いではありません。
「何のために、自分自身が目標を達成しない選択をしているのか?」という視点で考えることが大切なのです。
学習塾の先生の実例
この考え方を説明するために、ある学習塾の先生のエピソードをご紹介したいと思います。
その先生は、以前、私に集客の相談をしてくださった方です。
時期としては、2023年5月8日、つまり新型コロナウイルスの法律上の分類が「2類」から「5類」に移行した頃でした。
いわゆる「コロナが明けた」と、一般的に認識されていた時期ですね。
そこから半年ほど経った2023年11月頃、その先生は「生徒がなかなか増えない」とのことで、私に相談をしてくださいました。
お話を伺うと、コロナ禍の影響で一時的に生徒数が減少したものの、「コロナが明ければ生徒が戻ってくるだろう」と考えていたそうです。
しかし、実際にはコロナが明けて半年が経過しても、思うように生徒が戻らず、集客に悩まれていました。
そこで、私は教室の現状について詳しくお伺いし、それを踏まえて具体的なアドバイスをさせていただきました。
教壇から離れて見失った本来の役割
そのやり取りの中で、特に印象的だったエピソードがあります。
今後の改善策を考える中で、先生がふと「生徒に熱い話をしたいと思います」とおっしゃったのです。
「熱い話」とは何か、詳しく聞いてみると、先生はこれまで授業の中で、生徒たちに人生観や価値観について語っていたそうです。
例えば、「社会とはどんな場所なのか」「なぜ人は働くのか」「お金を稼ぐとはどういうことなのか」といったテーマです。
まるで『金八先生』のように、ただ勉強を教えるだけでなく、生徒たちが将来幸せに生きていくための知恵を授けていたのです。
しかし、教室の評判が広がり、生徒数が増えるにつれて、先生は授業を担当する機会が減っていきました。
新しい講師を採用し、授業の多くを任せるようになったことで、先生自身は管理業務や経営の仕事が中心になり、直接教壇に立つことが少なくなっていったのです。
その結果、生徒に「熱い話」をする機会がほとんどなくなってしまいました。
再び立ち戻った原点
ここで先生は気づいたのです。
「自分がやりたかったことは、生徒に学問を教えるだけでなく、人生について語り、成長をサポートすることだったのではないか」と。
この気づきが、教室の経営を見直すきっかけとなりました。
先生は「何のために目標を達成させないのか?」という問いを自分に投げかけ、そこから改善のヒントを見つけたのです。
この話を通して、皆さんにもぜひ考えてほしいのです。
「なぜ目標が達成できないのか?」ではなく、「何のために目標を達成しないのか?」と問いかけることで、思いがけない気づきが得られるかもしれません。
そういう話を聞いた上で、先生ご自身は「これから改めて生徒たちに熱い話、つまり人生論を伝えていきたい」と考えられたそうです。
生徒たちからの感謝の手紙
そこで、私はひとつ確認してみました。
「もし、先生がこれから生徒たちに人生論や熱い話を伝えるようになったら、生徒の皆さんはどのように変化していくと思いますか?」
すると、先生は即答で「それはもう、うちの塾をもっと好きになると思います」とおっしゃいました。
なぜそう思うのか伺うと、先生は過去に熱い話をして生徒から好かれていた経験があったからです。
その話を踏まえて、改めて「やはり先生としても、生徒たちに人生論を伝えていきたいというお気持ちがあるのですか?」とお伺いすると、先生はこれも即答で「話したいです」とおっしゃいました。
さらに、後から分かってきたことなのですが、かつて先生が主に教壇に立ち、人生論を伝えていた頃の生徒たちは、卒業の際にA4の便箋2〜3枚にびっしりと感謝の言葉を書いた手紙を先生に渡していたのです。
しかも、この話を聞いた後、先生は「ホームページでも紹介しているんですよ」とおっしゃいました。
実際に拝見すると、そこには生徒たちが直筆で「先生がいなかったら、今の自分はありません」といった内容を、A4の便箋2〜3枚にわたってびっしりと書いた感謝の手紙が掲載されていました。
しかも、それが1人や2人ではなかったのです。
私がざっと確認しただけでも、20人以上の生徒がA4の便箋2〜3枚に感謝の言葉を書いていました。
無意識の選択が示すもの
そこで、私は改めて先生にお聞きしました。
「もし今日のアドバイスを実践して生徒が増え、教室がさらに大きくなったとしたらどうでしょうか?その場合、新たに多くの講師を雇う必要が出てくるかもしれません。そして、先生が教壇に立たなくなることで、人生論を伝えられない学習塾になってしまうとしたら、どう思いますか?」
すると、先生は「それは嫌です」と即答されました。
ここまでのお話を伺い、私はなぜ先生が生徒を減らしたのかが分かりました。
先生は生徒が減ったことで、集客に関する相談を私にしてこられたのです。
つまり、「今よりも生徒を増やしたい」という目標があったわけです。
しかし、実際には生徒が増えなかった、あるいは減ってしまった。
ここで、今回の問いかけが重要になります。
- 「何のために、私は目標を達成させなかったのか?」
- 「何のために、自分自身で生徒を減らしたのか?」
この問いを深く考えてみると、答えが見えてきます。
今回のケースではどうだったでしょうか?
生徒が減ることで、経営面から見ると講師を雇えなくなります。
そうなると、結果的に先生自身が教壇に立たざるを得ない状況になります。
するとどうでしょう?
先生が教壇に立つ機会が増え、人生論を伝えることができるようになります。
本当に望んでいた学習塾の姿とは
逆に、今の組織体制のまま生徒がさらに増えた場合はどうでしょうか?
生徒が増えるほど、より多くの講師を雇う必要が出てきます。
結果として、先生は講師たちを管理する役割に専念することになり、ますます教壇に立つ機会を失ってしまいます。
しかし、それは先生ご自身が本当に望んだ学習塾のあり方だったのでしょうか?
先生が本当にやりたかったのは、生徒たちに人生論を伝えながら、単なる勉強だけでなく「社会で豊かに幸せに生きていくための力」を育むことだったのではないでしょうか?
先生は、その想いを胸に授業をしていたはずです。
ところが、気づかぬうちに、プレイヤー(教壇に立つ立場)からマネージャー(経営に専念する立場)へと移行してしまったのかもしれません。
もしかすると、「経営者として組織を大きくしなければならない」という考えが無意識のうちに働いていたのかもしれません。
しかし、その結果として、先生が教壇に立つ機会が減り、人生論を伝える時間もどんどん減っていった。
そして、それが先生にとって「本当に望んでいた学習塾の姿ではなかった」ということに気づき始めたのです。
無意識の選択が導いた「本来の在り方」
だからこそ、先生の無意識は「生徒を減らす」という選択をしたのではないでしょうか?
「自分が本当にやりたい経営を実現するには、生徒を減らさなければならない」と、無意識が判断したのかもしれません。
あるいは、「本当の自分」がそうさせたのかもしれません。
私たちの「内なる本当の自分」は、実は自分自身の本当の願いをよく知っているのです。
そして、その「内なる自分」というものは、本当に望んだものを実現させるためには、手段を選ばないのです。
表面的に見れば、生徒が減ってしまうと困りますよね。
売上が下がると、講師への給与が支払えなくなったり、生活が成り立たなくなったりといった問題が生じます。
しかし、本当の自分が本当に望むことを実現しようとするとき、その手段にはこだわりません。
場合によっては、生徒を減らすという現象を、現実に引き起こすことすらあるのです。
ここまでの話を聞いていただくと、今回のケースにおける先生にとって「本当にやりたい塾経営」というのは、単に生徒を増やすことではなかったのだと気づかれるのではないでしょうか。
むしろ、自分が本当にやりたい塾経営を実現するために、生徒を減らすという現象を、無意識のうちに自ら引き起こしていたのです。
そう考えると、「生徒が減る」という出来事は、必ずしも悪いことではないという見方もできるはずです。
「達成できない理由」に隠された本当のメッセージ
「なぜ生徒が減ったのか?」ではなく、「何のために生徒を減らすという現象を自分が引き起こしたのか?」と問いかけることで、それを理想的な経営を実現するためのチャンスと捉え直すことができます。
このように、自分の目標が思い通りに達成できないとき、それは何かしらの必要があって起きている場合が多いのです。
だからこそ、そういうときこそ、自分に問いかけるべきことがあります。
それは、「何のために自分がその現象を引き起こしているのか?」という問いです。
ここで注意すべきポイントは、「なぜそれが起きたのか?」と考えるのではなく、「何のためにそれを自分が起こしたのか?」と問いかけることです。
なぜなら、「なぜそれが起きたのか?」と考えると、「コロナの影響で……」「景気が悪いから……」といったように、自分の外側に原因を求めてしまうからです。
しかし、それでは本質的な問題の解決にはつながりません。
大切なのは、「どういう必要があって自分がその状況を引き起こしているのか?」と、自分自身が主体となって問いかけることです。
自分がそれを引き起こしているという当事者意識を持つことで、解決策の糸口が見えてくるのです。
本当のゴールを見つけるために
もちろん、こうした問いかけは、普段あまりしないものかもしれません。
ですから、この問いを自分に投げかけても、すぐに答えが出るとは限りません。
しかし、この問いを持ち続け、考え続けることが何よりも大切です。
問い続けることで、ふとお風呂に入ってリラックスしているときや、何気なくつけたテレビのセリフなどから、答えにつながるヒントを得ることもあります。
「ああ、そういうことだったのか!」と、ある瞬間に腑に落ちるような気づきを得ることもあるのです。
逆に、すぐに出てくる答えというのは、案外本質的なものではないこともあります。
本当に大事な答えは、時間をかけて自分の中でしっかりと消化し、「これだ!」と腹落ちするものなのです。
だからこそ、もし今、目標が思い通りに達成できない状況にあるならば、ぜひ今回紹介した「何のために自分がそれを引き起こしたのか?」という問いを、自分自身に投げかけてみてください。
その問いの先には、あなたが本当に求める「理想の経営」「理想の人生」につながる真実があるはずです。
ぜひ、ご自身の手で、その真実を掴み取っていただきたいと思います。
まとめ
目標が達成できないとき、それは単なる失敗ではなく、本当の自分が何かを伝えようとしているサインかもしれません。
「なぜできないのか?」ではなく、「何のためにこの状況を自ら作り出しているのか?」と問いかけることで、新たな気づきを得ることができます。
今回の学習塾の先生の例のように、表面的な課題の裏には、本当に大切にしたい価値観や願いが隠れていることもあるのです。
もし今、目標が思うように進んでいないと感じるなら、一度立ち止まって、自分の内なる声に耳を傾けてみてはいかがでしょうか?